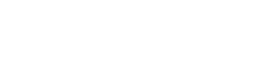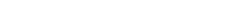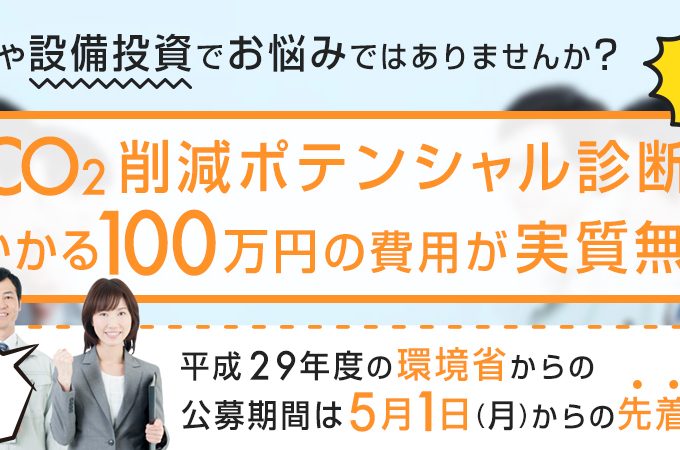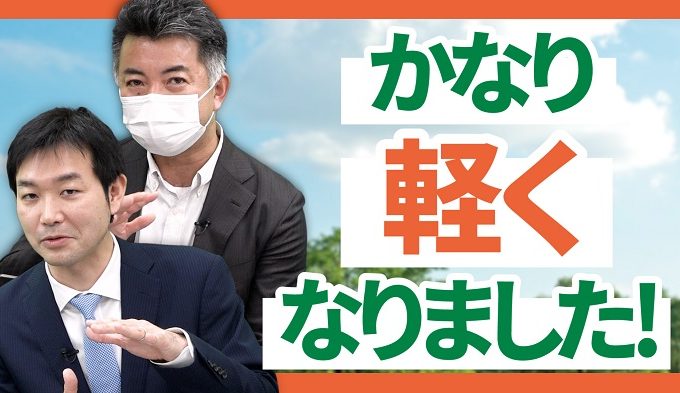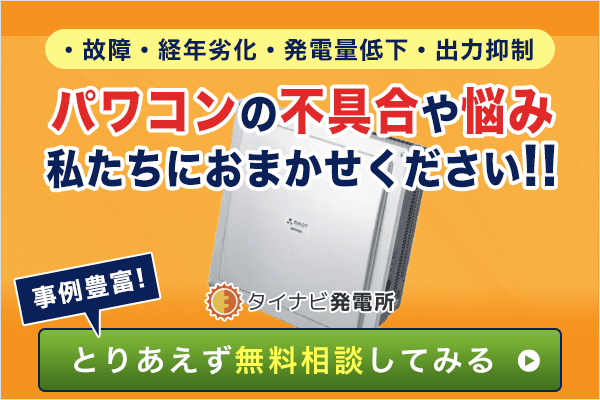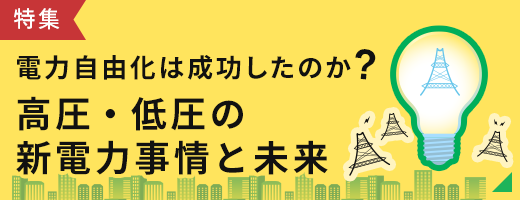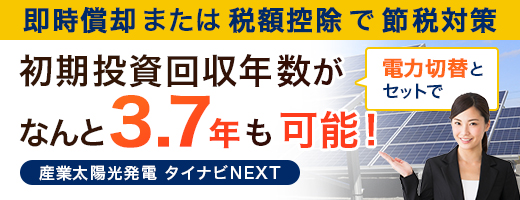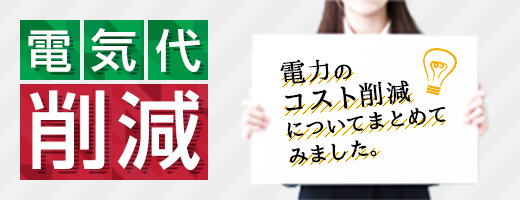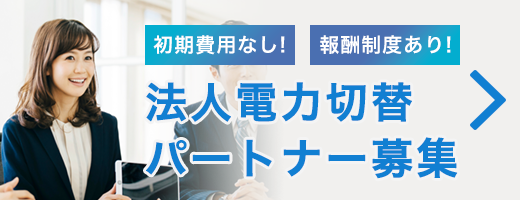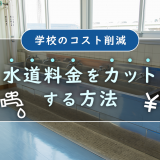直接材料費と間接材料費の誤解されやすい4つの違いについて

生産活動は様々な経費が組み合わされて成り立ち、基本的に生産にかかる費用は直接費と間接費に分けられます。まず生産におけるこの2つの費用は、更に3つの費用に細分化されるでしょう。それが、材料費/労務費/その他の経費になるのです。
その内、材料費は製品の直接的な費用に関わる重要な概念になりますが、直接材料費/間接材料費という考え方にて管理されていきます。しかし、生産の現場にて原価計算を進められる方もその費用参入に迷われる方も少なくなく、財務キャリアの経験の少ない人ほどこのような傾向になるでしょう。
今回は直接材料費と間接材料費の違いについて解説を進めながら、各生産現場においてどのようなものが各々の材料費に含まれるかもチェックしていきます。
直接材料費と間接材料費の基本的な違い

ここでは、まず直接材料費と間接材料費の違いを見ていきましょう。この2つの違いは一言で表すと、製品の中にそれが必要不可欠なものとして明白に組み込まれているかいないかになります。
各種の製品を生産していく場合に直接費に含まれるのは比較的小さな部分になり、その中でも材料費は言葉通りに分かりやすい概念なのですが意外に、直接材料費と間接材料費はいまだに混同される部分も多いのです。ここでは、両者の基本的な構成内訳をチェックしましょう。
直接材料費に関する基本的な構成内訳
まず直接材料費の構成内訳を具体的に見ていくと、素材費/原料費/買入部品費に分けられます。しかし、生産元で扱われる材料消費がこのどれかに含まれるものかは大きく異なるでしょう。
通常において素材費というのは単純加工に使われる材料を指すことが多く、ファブリックや紙などの加工後も目で確認できる材料となります。
原料費になると気体/液体/個体に関わらず、成型するための材料になるものを指すことが一般的です。前述の紙になると製紙メーカーでは当然ながら素材になりえず、原料費にて木材や原油などの消費がなされる訳です。
また、買入部品費は直接材料費の中でも一番分かりやすく、製品の組み立てに使うネジや製品の本体に取り付けるオプションパーツなどが主なものになるでしょう。
間接材料費に関する基本的な構成内訳
次に、間接材料費についての基本的な構成内訳を見ていきます。間接という言葉に多くの方が惑わされ、実際のところ費用の分類に苦心されている原因としてこの事情も大きいのです。
間接材料費は通常において、補助材料費/消耗品費/消耗工具器具備品費に主に分けられます。間接材料費は定義が曖昧である部分もあり、シンプルに言えば直接材料費に含まれないものはすべてここに含まれるという理解が最も適当でしょう。
この内、補助材料費は理解も複雑な面が多く、製品を最初に作る際やメンテナンスや修理に用いられる副材料消費を指すことが通常です。
消耗品費は、製品が完成してからのシュリンクやパッキングなどの包装材料などがケースとして分かりやすいと言えます。
消費工具器具備品費は、生産に必要な工具であっても耐用年数が1年未満とされる消耗品としての性質の高い安価なものに適用されることが多いでしょう。
直接材料費への算入は実務的にメーカーによって異なる

さて、これまでの説明を見てみれば直接材料費への振り分けはとても単純だと理解されたはずです。ただ、同じタイプの製品であっても、メーカーによって実務上にて同じような材料の消費について直接材料費として計上されていないこともあります。
つまり、メーカーが異なれば経費算入をしているか否かについて大きく差があるのです。これが、具体的にどのような意味を持っているのかをここで見ていきましょう。
1つの製品を作るための材料構成が明確である必要性
多くのメーカーにおいて、材料の消費を正確に管理するために生産管理システムを導入しています。このシステムは、どの製品にどの材料をどれだけ使うかを明確にするシステムで、多くの場合は財務上でも役立てられるようにデータ連結がなされているでしょう。
つまり、メーカーごとに生産のための仕様を決めるとそれに使われる材料についての情報が生産管理システムに反映されることになります。この時点において、直接材料費として使われるべき材料が決まってくる流れになるのです。
これに含まれないと財務上は直接材料費として計上できないことになり、あらかじめこれを使用すると明確にしていなければならないと言えます。よって、材料の構成はメーカーによって大きく違うために、直接材料費の内訳に関しても当然異なってくるのです。
直接材料費と間接材料費に含まれる具体的な事例

ここからは、直接材料費と間接材料費をいろいろな製品を用いて事例を挙げていきましょう。
基本的な構成内訳はもうお分かりになっていると思いますので、あとはいろんな具体例を見て覚えていくことが求められるのです。早速、直接材料費と間接材料費をさらにひも解いていきます。
直接材料費として扱われる材料事例
直接材料費では、日常的に欠かせない存在であるパソコンやスマホをまず例にあげましょう。現在におけるこのようなIT機器は組み立て加工式になっていますので、メーカー自体が原料費として購入するものは極めて稀です。
基盤/筐体/ネジなどは素材費や原料費ではなく、既製品のパーツとしての買入部品費として挙げられることが多くなるでしょう。仮に筐体もメーカーで成型生産するのであれば、材料のプラスチック片などが原料費として計上されます。
その一方でケーキなどのスイーツを作る場合は、卵に小麦粉に生クリームエッセンスなど多くの材料が原料費として消費されます。また、ケーキの上に乗せられるイチゴなどは加工せず載せられる場合になると、買入部品費として計上されるでしょう。
このように、製品の製造法によって材料消費の形態も大きく異なりますので、費用振り分けにも影響してくるのは言うまでもありません。
間接材料費として扱われる材料事例
次に間接材料費についてですが、先に説明したように直接材料費に含まれない材料費として考えます。消耗品であっても。パソコンやスマホなどの耐久財は、説明がしやすいので再びこれらを例に挙げましょう。
パソコンやスマホを生産する場合、液晶や基盤そして筐体などを取り付けることになります。ここで使用される場合は、液晶部分や基盤や筐体などの材料は直接的なものですが、これらを配置する作業に使う接着剤やはんだ類などは生産管理システムの材料引き当てのための構成内容に含まれていません。
この生産時に確実に消費されているのに、商品を作るための構成内容には見えないものを主に間接材料費のうち補助材料費に含まれることがほとんどです。そのため、直接材料費として挙げるためには、材料の引き当てが確実にできるかどうかが重要なことはこの点でも理解できます。
材料費に関して誤解しやすい大きなポイント

ここまで来れば、材料費における直接的間接的な使い方は明らかです。それでも、材料費全般に関して、実は誤解しやすい大きなポイントも存在しています。
メーカーに勤めていても勘違いされることもある材料費についての考え方になりますが、ここでは材料にまつわる再確認しておきたい事項をご説明しましょう。
材料は実際使用されて材料費として計上される
材料について実に多くの方が理解されていない大きなポイントとして、材料は使わなければ材料費にならないということです。つまり、材料はお金を使って入手しますが、ただ入手しただけでは倉庫に保管されているだけの資産に過ぎません。
これが生産で消費される段階で資産が使われることになり、その紐づけとして材料費として計上されることになります。そのため、材料の正確な管理はメーカーである企業の資産保有額に大きく影響することになり、企業としての信用度を図る基準にもなりますので財務担当者が常に口うるさくなるのは、このためです。
現実的な話をすると、生産管理システムの在庫管理データが正確なメーカーほど、材料費に関する財務管理もより正確になっていると言えるでしょう。
パッキング用の袋や材料は直接材料に含まれることもある
間接材料費について、製品の包装に用いられるものは間接材料費に含まれると説明しました。しかし、これは企業の製品仕様によっては絶対的でないこともあるでしょう。
多くのリテール品、つまり小売り用の単品製品になると、パッキング用のビニール袋やシュリンク材も多くの製品で使われる共通部材が消費されます。それでも、メーカーによってはビニールや紙のパッキング材なども含めて、完成品の構成内容としている場合もあるのです。
このような場合になると、たとえパッキング材料であっても直接材料費に含まれることが多くなり、この場合は生産管理システムの中の引き当て構成にもきちんと含まれている紐づけがなされています。
ビニール袋にも様々なサイズが存在していることもあって、一概に間接材料費に含まれているとは言い切れない事情がここに存在しているでしょう。
営業利益を改善するコスト削減は「電力見直し」
事業の収支改善にご興味はありませんか? 今の売上のままで営業利益をあげるには「電力会社の見直し」です!
いまの情勢は、売上を伸ばすよりも電力乗り換えで支出を抑えるほうが簡単です。照明や空調も変えない、今の営業スタイルを維持しながらでも、電力コストは減らせるからです!
高圧電力は、年間の最大需要電力で基本料金を決めています。つまり、年間で最大のピーク時だけでも電力の消費量が跳ね上がれば、その水準に基本料金が調整されて、その先もずっと高い契約になってしまうということです。逆に、電気料金プランを見直せばムダのない契約ができ、光熱費を抑えて営業利益を増やせるというわけです。
高圧電気料金が高額になってしまう3つの要素
高圧電力の電気料金に影響するのは、次の3つです。
- プランによって差がある「基本料金の単価」
- 設備と電気の使用状況「力率」
- 電力需要の多さで決まる「契約電力」
こうして並べた3つをどうやって改善するか、なかなかピンと来ませんよね。それぞれの解決策を挙げてみましょう。
- 電気料金プランの切り替え
- 力率改善
- 最大電力需要を抑えるピークシフト
力率改善とピークシフトには、設備の買い替えや電力を管理するシステムが必要で、つまり初期費用がかかってしまいます。手軽に試すにはハードルが高いですよね。
1円の追加投資も払わずに試せる方法はひとつだけ、「電気料金プランの切り替え」です。実は企業向けの電気料金プランも簡単に変えられますし、停電や電力不足のリスクが変わるという事実もないんです!
電力コスト全体の削減をご検討なら、まずは複数の電力会社から見積もりをとって比較してください。同じ電気なのに、電力会社やプランによって支払額にずいぶん差があることに驚くはずです。
電力に詳しくない方もOK! コスト削減のサポートは「スイッチビズ」

事業用の電力コストを削減するなら、スイッチビズをご利用ください。新しい電気料金の見積もり取得から比較、乗り換えまで、専任のコンサルタントが無料でサポートいたします。
ぜひ、高圧・特別高圧施設でコスト削減をする第一歩としてお試しください。